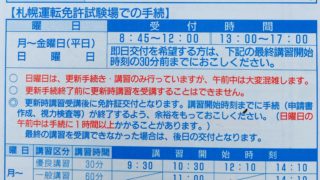大晦日の札幌を舞台にした橘外男の「求婚記」はロマンチックなプロポーズの話などではなく、鉄道工場での惨めな暮らしから脱出を目論む男の悲しい物語だ。舞台となった大正時代の札幌苗穂地区の描写が興味深いので、少し詳しく書いておこう。
橘外男とは
橘外男は大正時代から戦後にかけて活動していた小説家で、明治末期から大正初期にかけての4年弱を札幌で過ごしたことがある。もともと金沢の出身者だが、あまりの素行の悪さに困り果てた両親は、18歳のとき、遠く北海道の地にまで息子を飛ばしてしまう。札幌では、鉄道院札幌工場の工場長をしていた従兄の元に預けられ、苗穂の玉葱畑の真ん中にあった鉄道工場合宿所で暮らす。
当時、橘は鉄道工場での仕事にも馴染めず、薄野や狸小路で追剥を繰り返した末、鉄道工場の公金横領により懲役刑を受ける。服役後は朝鮮で小さな貿易商を興したりするが、両親から勘当を許してもらうという目的で小説を書き始める。
大正11年から12年にかけて発行された「太陽の沈みゆく時」シリーズは、大正初期の札幌をロマンチックに描いており、道内でもたくさんの人に読まれたらしい。昭和13年には「ナリン殿下への回想」で第7回直木賞を受賞。戦後も人気作家として活躍を続けるが、昭和34年、65歳で没した。
あらすじ
舞台は大正時代初期の札幌苗穂。不良少年の私は18歳のとき、両親から愛想を尽かされ、叔父が工場長を務める鉄道省札幌工場で臨時職員として働くこととなり、工場近くにある苗穂の職工合宿所で暮らしている。
親戚との折り合いも悪く、将来への希望が持てない日々を過ごす中、工場ではブラジルへの移民を希望する職工が増えていた。ブラジル拓殖移民会社の募集に応募すれば、船でブラジルまで連れていってもらえる、しかも、ブラジルでの農業は、金がもうかって仕方がないという。詳しいことは何も分からないけれど、とにかくブラジルにさえ行けば、一生遊んで暮らせるらしい。
私はブラジルへの移住を決意するが、この移民事業に応募する条件には妻帯者ということがあったため、独身の私は、一緒にブラジルへ行ってくれる女性を探し、近所の駄菓子屋で時々見かける若い女性を候補として考える。私は、駄菓子屋の婆さんになけなしの金を渡して仲介をお願いし、婆さんは気前よく引き受けて金まで受け取ったものの、一向に返事が来ない。
年の暮れのある日、やむを得ず私は自らその女性のもとを訪ねて、結婚の意思を確認するが、女性のもとへはお婆さんからの仲介は一切なく、求婚の話さえも初耳だという。おまけに、女性の顔を改めてよく見ると、とても結婚しようという気持ちにはなれないような容姿で、激怒した私は、駄菓子屋の婆さんと大喧嘩をして、失意のどん底のうちに寂しい年越しを迎えるというストーリー。
はっきり言って、クズ男によるクズのような物語だが、大正時代の苗穂の様子が詳しく描かれているので、個人的にはまあまあ気に入っている。以下、札幌に関する描写を拾い上げてみよう。
初めての北海道の冬
私にとって初めての北海道の冬。恐ろしくサラサラと乾いた雪が降って、それが積もってからは空が薄鼠色の暗澹とした北国特有の陰鬱極まるものに変わった。隙間もなく空処を埋めたね雪の中に屋根の急勾配をした家々も葉の落ちたアカシヤ、藻岩、手稲の山々も黯ずんだ物音はこれからの長い長い雪の明け暮れを迎えるように寒々と凍て付いていた。
北海道の冬を初めて過ごす者が抱える大きな不安は、今も昔もあまり変わらないのかもしれない。北海道らしい雄大な大自然ですら、冬の脅威を象徴する存在となって現れてくる。「屋根の急勾配をした家々」も、作者にとっては北海道の冬を象徴する存在に思えたのだろうか。
札幌の出面取り
出面取りというのは、どういう字を当てはめるのか知らなかったが、札幌では日雇いの労働者になって石炭の積み降ろしや除雪人夫に出たりしている者のことを、出面取りと呼んでいた。
「出面取り」という言葉は、今ではほとんど聞かれなくなったが、現在で言うと「日雇い労働者」ということになるだろう。当時の札幌では、日雇い労働でその日暮らしをしながら日々生きている貧困層の人たちも少なくなかったらしい。
鉄道工場近くの駄菓子屋
工場の正門から半町ばかりも離れた職工町の入り口に、潰れかかった貧乏ったらしい駄菓子屋があって、そこには死んだ亭主がもと工場の職工だったとかいう五十位の因業そうなお婆さんが一人で店番をしていた。
鉄道工場の職工町の雰囲気を伝える描写の一部分。物語では重要な役割を担う駄菓子屋のお婆さんの暮らしぶりが伝わってくる。
麦酒会社通り
夕方退けて帰る時、私は顔見知りの麦酒会社通りの古本屋へ持って行って、無理やりにそれを一円五十銭に買ってもらった。
札幌麦酒会社は、現在サッポロファクトリーとして利用されている煉瓦造りの建物のことだと思われるが、現在、北3条通りと呼ばれている通りが、当時は「麦酒会社通り」と呼ばれていたのかもしれない
苗穂の職工町
婆の説明によると、あの娘はおたさんという子で、この三四町先の煙草屋と荒物屋との間を入った職工町の、一町ばかりいった左側の長屋の二軒目で、横山さんという職工と渡辺さんという職工とのすぐ脇に、兄さんたちと一緒に暮らしているという事であった。兄さんというのも職工かと聞いてみたら、「うんにゃ」と婆は頭を振った。もとは魚屋という事だったが、今はおちぶれて出面取りをしているらしいという事であった。
鉄道工場のあった苗穂地区には職工町が多かったらしい。職工というのは、工場で働く技術職の職員のことだが、生活環境の描写などを読むと、決して優遇されていたわけではないことが伝わってくる。
苗穂の貧民窟
私はかねて聞いていたとおり煙草屋と荒物屋との間の狭い横丁を入った、職工町の一町ばかり先の左側を目指して行ったが、どうも何ともかともごみごみとした、行けば行くほど裏長屋の貧民窟のような処であった。降り積もった雪が腰のあたりまで両側に掃き寄せられて、そのトンネルみたいな中を平ったくなって入って行った芥溜(ごみため)のあたりから、同じような小さな棟割り長屋が幾つも幾つも立ち並んでいた。
苗穂の職工町の外れまで行くと、貧民窟のような裏長屋が現れてくる。当時の札幌は、社会福祉事業がまだ十分ではなく、貧富の格差が生活環境にそのまま反映されていて、札幌市内にも貧民窟と呼ばれるような貧困地区がいくつもあったという。
大晦日の餅つき
おたの家というのは、其の角から二軒目であったが、これがまた大変な事には前の長屋と自分の家との狭苦しい廂(ひさし)の間に大きな臼を抱えて、明日がお正月だというのに今頃になって、ペッタンコペッタンコと餅を搗いている真っ最中なのであった。
大晦日に餅つきを行うことが一般的ではないことが分かる。大晦日になって、ようやく餅米を買うことができ、家族で餅付きをしている場面だったのだろうか。貧困地区の生活を知ることのできる貴重な描写だ。
年越しの雪
私は音もなく降りしきっている雪を窓の外に眺めながら、来月の給料日にはどんなことをしても合宿屋のオヤジに金を払わずにその金を持って、薄野とかにある女郎屋というものへ行ってみようと決心したのであった。そして、そう思いながら、サラサラと窓に当たる胸に沁み入るような大晦日の雪を聞きながら、九十五銭の年越しの金を持って身動きもせずに、囲炉裏の端に座り込んでいた。
物語の最後の場面では、夢破れて年越しを迎えようとしている男の絶望感が、しみじみと伝わってくる。読者としては、クズ男の馬鹿げた計画が破たんすることで、どうにか救われる思いがしたというところか。
なるほど!文学散歩
何度も繰り返すようだけれど、正直に言って作品としての価値はそれほど高くはないと思う。ただ、昔の札幌を知る上での貴重な記録のひとつとして、未来に受け継いでいきたい作品だと思う。そんな文学の愛し方もあっていいんじゃないかな(笑)