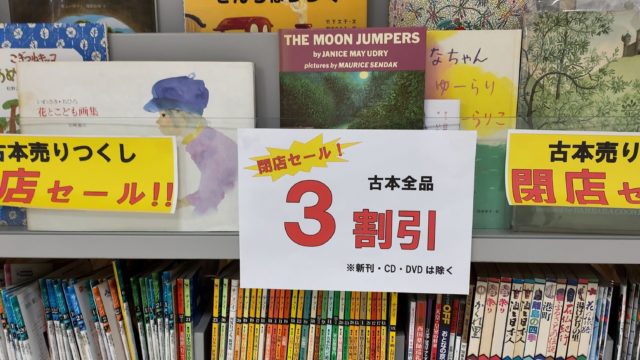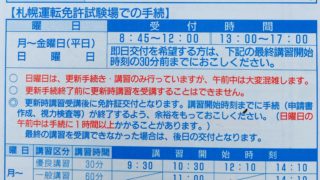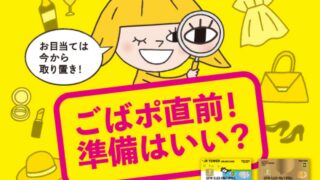みんな大好きムーミン物語、もちろん札幌でも大人気。
北の街札幌は、ムーミンの祖国フィンランドに、どこか似ているところがあるようです。
今回は「ムーミン谷の十一月」を読みながら11月の札幌を歩いてみました。
それとなく北欧っぽい晩秋の札幌を探してみてくださいね。
「ムーミン谷の十一月」のこと
「ムーミン谷の十一月」は1970年に書かれました。
ムーミン物語シリーズの最終巻です。
作者はもちろんトーベ・ヤンソン。
小説として第9作目の作品でした。
「ムーミン谷の十一月」にはムーミン一家は登場しません。
冬を前に、ムーミン一家はどこか旅に出かけてしまったようです。
そうとも知らないムーミン谷の住民たちがムーミン屋敷に集まってきます。
訪問者たちはムーミン屋敷を舞台に奇妙な共同生活を始めます。
めいめいが自分勝手で自己中心的な登場人物ばかり。
最初は衝突を繰り返していますが、少しずつ互いを理解するようになります。
自分の個性を尊重しながら、互いの個性を尊重する。
最近流行語のダイバーシティの考え方が、物語の中では実践されています。
多様性社会がムーミン屋敷を舞台として展開されているのです。
今回は、そんな「ムーミン谷の十一月」の世界を少しだけご紹介しましょう。
「ムーミン谷の十一月」名言集
ムーミン物語には人生哲学があります。
豊かに生きるためのヒントをムーミン物語から探してみましょう。
今回ここで引用している文章は、講談社の青い鳥文庫「ムーミン谷の十一月」(トーベ・ヤンソン・作、鈴木徹郎・訳)から引用させていただいています。
あいつ、旅に行っちまったよ。秋になったんだねえ
あとで友だちが、目をさましたら、こういうでしょうね。
「あいつ、旅に行っちまったよ。秋になったんだねえ」って。
スナフキンは、しずかに、かろやかに、歩いていきました。
まわりは、すっぽりと、森につつまれました。
スナフキンが旅に出るのは、季節の変わり目のときです。
一度出発したスナフキンが戻ってきたのは、季節の変わり目に、まだ少し早かったからかもしれませんね。
冬もまぢかな、ひっそりとした秋のひとときは
冬もまぢかな、ひっそりとした秋のひとときは、寒々として、いやなときだと思ったら大まちがいです。せっせと、せいいいっぱいの冬じたくのたくわえをして、安心なところにしまいこむときなのですからね。
人生には冬の季節も必要。
冬は自分自身としっかりと向き合う季節でもあるのです。
朝のコーヒーは、いつも、ベランダでのむきまりになっていたんだよ
ヘムレンさんは、おぼんにコーヒーをのせて、応接間へはこんでいき、マホガニーのたまご形のテーブルの上におきました。
「朝のコーヒーは、いつも、ベランダでのむきまりになっていたんだよ」
ムーミン谷の仲間たちはコーヒーが大好きです。
北の国で暮らす人たちにとって、コーヒーは生活と密着している飲み物だったのでしょう。
目がさめてみると、その人は、自分の名まえをわすれていました
目がさめてみると、その人は、自分の名まえをわすれていました。人の名まえをわすれると、ちょっと、ゆううつになりますが、自分の名まえをわすれることができるのは、とてもすばらしいことです。
ときに、人は自分の名前を忘れてしまいたくなるものです。
名前や肩書のない一人の純粋な人間として生きるために。
こいつはもみじだな。こいつの名まえは、けっしてわすれないぞ
最後までちりのこっていた、赤や黄色の木の葉がちり、歩いていくおじさんの足のまわりで、ぴょんぴょんはずみます。ときどき、おじさんは、足をとめて、つえの先でおち葉をつついてひろいあげ、ひとりごとをつぶやきました。
「こいつはもみじだな。こいつの名まえは、けっしてわすれないぞ」
自分の名前を忘れても「もみじ」の名前は忘れない。
スクルッタじいさんは自然を敬愛しているのです。
だれかと出会って、すぐあとで、その人のことをわすれたからといって、ちっとも気にしませんでした
なにがすてきだといったって、たのしくすごすことぐらいすてきなことは、ほかにないし、また、わけもないことなんです。ミムラねえさんは、だれかと出会って、すぐあとで、その人のことをわすれたからといって、ちっとも気にしませんでした。
ミムラねえさんは自分が一番大切だと考えています。
そして、自分と同じくらい周りの人たちのことを大切に考えています。
きょうも、また、十一月の一日がしずかにくれていきました
きょうも、また、十一月の一日がしずかにくれていきました。ミムラねえさんは、羽ぶとんの中にもぐりこみました。足をのばすと、こつんとつま先がぶつかったので、つま先をまげて、あんかをはさみました。
11月は秋から冬へと季節が変わる大切な月です。
寒い夜は羽根布団とあんかで温かく過ごしましょう。
ねむたくなればねむり、おきたほうがいいときはおきる
ミムラねえさんは、ゆめなんて見ません。ねむたくなればねむり、おきたほうがいいときはおきる。それがミムラねえさんなのです。
ミムラねえさんは「自然に生きる」ことを大切にしています。
自然のなりゆきに任せることも、また、自分らしい生き方なのです。
ブラックコーヒーを一ぱいのんだら、もうぼくのものだ
「ブラックコーヒーを一ぱいのんだら、もうぼくのものだ」
たき火に火がついて、朝ぎりの中でもえだしました。
スナフキンは、コーヒーポットに小川の水をいっぱい入れて、火の上にのせました。
スナフキンはコーヒーが大好きです。
コーヒーを飲みながら大好きな音楽を作ります。
きみ、コーヒーにおさとうを入れるかい?
「きみ、コーヒーにおさとうを入れるかい? それとも入れないほうがいいかい?」
「入れてくれ。できれば四つな」と、ヘムレンさんは答えました。
スナフキンはブラックコーヒー派です。
でも、お客が来たときのために、ちゃんとお砂糖を用意しています。
ベランダでは、みんながベンチにこしかけて、コーヒーをのんでいました
ぶらりぶらり、フィリフヨンカは、階段をおりていきました。ベランダでは、みんながベンチにこしかけて、コーヒーをのんでいました。
仲間たちが集まるところにコーヒーあり。
コーヒーはみんなの気持ちを温かく癒してくれるのです。
きゅうにスナフキンは、ムーミン一家がこいしくて、たまらなくなりました
はっと、きゅうにスナフキンは、ムーミン一家がこいしくて、たまらなくなりました。ムーミンたちだって、うるさいことはうるさいんです。おしゃべりだってしたがります。どこへいっても、顔があいます。でも、ムーミンたちといっしょのときは、自分ひとりになれんです。
一緒にいてさえ一人になれる。
互いを尊重する社会とは、そういう社会のことなのかもしれませんね。
空が黄色にそまって、まわりの山々が、かげ絵のようにくっきりうきでて見えるきりです
入り日は、もう、まるっきり見られなくなりました。日のしずむころは、空が黄色にそまって、まわりの山々が、かげ絵のようにくっきりうきでて見えるきりです。毎日が、井戸の中の一日のようなんです。
緯度の高い地域は日が早く沈みます。
夏の残照が長いだけに、秋の夕暮れは本当に寂しいものです。
「そこに、おさとうがあるよ」と、スナフキンはいいました
スナフキンは、魔法びんを出して、ジョッキみたいな茶わん二つに、紅茶をいっぱいつぎました。
「そこに、おさとうがあるよ」と、スナフキンはいいました。
スナフキンは紅茶も好きです。
コミュニケーションにお茶が欠かせないということを知っているのです。
あんまり、おおげさに考えすぎないようにしろよ
ホムサが帰るとき、スナフキンは、うしろからさけびました。
「あんまり、おおげさに考えすぎないようにしろよ。なんでも、大きくしすぎちゃ、だめだぜ」
ホムサには想像の中で自分の心配ごとを膨らませてしまう癖がありました。
彼の周りで起こる様々な心配事は、みんな彼の想像の中で創り出されたものだったのです。
「雪になるな」と、スナフキンはいいました
「ここは寒いよ」と、おじさんはいいました。
おじさんは、よっこらしょと立ちあがると、うちの中へ入っていきました。
「雪になるな」と、スナフキンはいいました。
雪が積もると季節は冬です。
共同生活をしていた仲間たちは、めいめい自分の居場所へと帰っていきました。
目がさめたときには、もうなにもかも、ちゃんと、そうでなければいけないようになっているはずだ
気持ちよくねむれるあなぐらを見つけて、ねむってしまうことだ。そのあいだに、世の中は世の中で、かってにどんどん日がたっていけばいいのだ。そうして目がさめたときには、もうなにもかも、ちゃんと、そうでなければいけないようになっているはずだ。
「時間が解決する」という言葉があります。
世の中の多くのトラブルは、時間がちゃんと解決してくれるのです。
ねむっているあいだも、だれかが自分のことを考えてくれていた、ということがわかることなんだ
でも、ホムサは、目がさめたときにたいせつなのは、ねむっているあいだも、だれかが自分のことを考えてくれていた、ということがわかることなんだ、といいました。
本当に怖いことは、自分の存在を忘れられてしまうこと。
一人が好きな人たちも、決して一人で生きていくことはできないのです。
三人は、コーヒーをのみに、うちにはいっていきました
三人は、コーヒーをのみに、うちにはいっていきました。そして、このときは、三人そろってコーヒーをのみ、おまけに、コーヒー茶わんの下には、しきざらまでしきました。
最後のコーヒーは、まるで別れのセレモニーのようでした。
大切なセレモニーの場面では、コーヒーカップにソーサを使うものなのです。
スナフキンは、コーヒーをつぎたしながらいいました
スナフキンは、コーヒーをつぎたしながらいいました。
「十二時すぎると、風が出てくるぞ」
風が吹くのを待って、スナフキンはヘムレンさんと一緒にヨットで海に出ます。
大風の中で、ヘムレンは「自分でヨットの舵を取る勇気」を見つけます。
ホムサは、コーヒーをついでやりました
ホムサは、コーヒーをついでやりました。ふたりは、食卓に、むかいあってこしかけました。なんだか、てれくさい気持ちでした。
海から戻ったヘムレンさんを、ホムサは温かく迎え入れます。
コーヒーを飲んだ後、ヘムレンさんは共同生活から独立していきました。
スナフキンは、テントの外に立っていました
スナフキンは、テントの外に立っていました。あたりがしんみりしてきました。もういつでも、旅に出かけられる用意ができていました。谷間は、じきに雪にとざされてしまいます。
ホムサ一人を残して、スナフキンは旅に出ました。
帰ってくるムーミン一家を迎えるのはホムサ一人でなければいけないことを、スナフキンは知っていたのです。
まとめ
「ムーミン谷の十一月」は知らない者同士が奇妙な共同生活を始める物語です。
そして、ひとつの季節の終わりとともに共同生活は終わります。
登場人物はみんな自己主張ばかりして衝突を繰り返します。
けれでも、やがて互いを理解し、尊重し、折り合いをつけながら暮らす方法を身に付けます。
みんなが互いを理解したとき、登場人物はそれぞれの居場所へと帰っていきます。
彼らはみなムーミン屋敷で少しずつ成長して、自分のうちへと戻っていくのです。
ムーミン物語はいつでも多くの示唆に富んでいます。
ひとつひとつの文章に作者の人生哲学が含まれているからです。
「ムーミン谷の十一月」は1970年に書かれた物語です。
半世紀も前に書かれたお話は、今も私たちの暮らしに何かを訴えかけているかのようです。