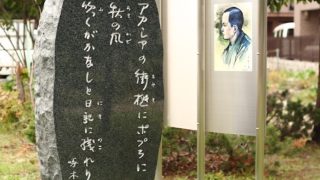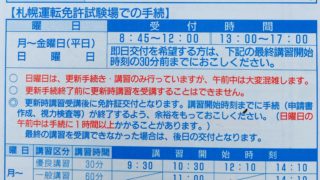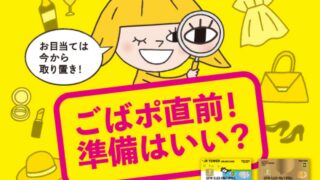真夏だというのに友部正人の「ニレはELM」ばかり聴いている。
この曲はみぞれ降る冬の夜のことを歌った歌なんだけれど、季節を問わずに聴きたくなる曲というのは確かにあるものだ。
みぞれ降る冬の夜に作者は咳をしている。
子どもの頃から体が弱くて咳ばかりしていたのだ。
作者はジャンゴ・ラインハルトの音楽を聴きながら、咳に効くと言われているお茶を飲んでいる。
要約してしまうと、この曲はただそれだけの内容である。
友部正人の多くの曲と同じようにドラマチックなストーリー展開も、あっと驚くような突飛な表現もそこにはない。
作者はただ淡々とお茶を飲んでいるだけだ。
それだけの内容なのに、どうしてこの曲はこんなにも胸の中に染み込んでくるのだろうか。
僕はこの曲のテーマは「郷愁」ではないかと勝手に考えている。
聴いている人々にこの曲は懐かしい何かを与えてくれるのだ。
みぞれ降る冬の夜に咳をしながら、作者は子どもの頃のことを思い出している。
小さな頃から喘息持ちで、いつも咳ばかりしていた。
そんな小学生の頃のことを、作者は一人きりで思い出している。
東京生まれの友部正人は小学校に上がるときに父の仕事の都合で札幌へ引越しをしている。
だから咳ばかりしていた頃の記憶はきっと北海道の冬の記憶だ。
見知らぬ北国の街で作者は咳ばかりしていたのだろう。
誰もがそうであるように、きっと作者にとってもいろいろのことがあった少年時代だったに違いない。
犬が吠えるような咳をしていた時代の自分と作者はしっかりと向き合おうとしている。
そんな少年時代を思い起こさせたのは、もちろん咳ばりではない。
激しく窓ガラスを叩くみぞれと、ジャンゴ・ラインハルトの物悲しいブルース、そして久しぶりにひいた咳の出る風邪が、作者を少年時代へと引き戻しているのだ。
それがどんな少年時代であったのか、作品の中で作者は一切触れていない。
思い出は常に作者自身の中にしか存在し得ないからだ。
僕たちが共有するのは、そこにある郷愁の思いだけでいい。
楡、カンゾウ、ユーカリの葉、レモンの皮。
作者は一人でお湯を沸かして咳に効くというお茶を飲む。
そこに過去の記憶と向き合う作者の姿が見えるような気がする。
札幌にある北海道大学はかつて「エルムの杜」と呼ばれたそうである。
札幌は古くからエルムの街だった。
そのことを考えると、この曲が「楡はELM」と名付けられた理由が分かるような気がする。
ニレはエルム。
みぞれ降る冬の夜にジャンゴ・ラインハルトを聴きながらひとり咳をしている作者がエルムの入ったお茶を飲むとき、遠い少年時代を過ごした北国のことを思い出したとしても、決して不思議なことではない。
ニレはELM。
この曲を聴きながら、僕は随分と久しぶりに子どもの頃のことを思い出している。