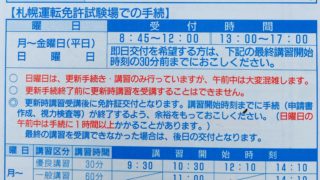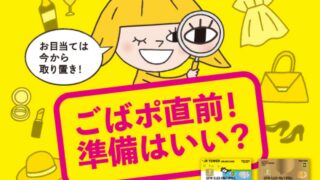鹿討豊太郎が、札幌農学校の講師として着任したのは、1894年(明治27年)5月のことです。
札幌農学校の第11期卒業生だった豊太郎は、札幌農学校長だった佐藤昌介との繋がりから、母校での就職となったようです。
当時、豊太郎の部屋は、札幌区篠路通四番地にありました。
そして、翌年の1895年(明治28年)5月、豊太郎は、佐藤昌介の妹・佐藤輔子(23)と結婚します。
この「鹿討豊太郎夫人」となった女性こそ、かつて島崎藤村が恋をした「初恋の女性」でした。
島崎藤村「初恋」のモデルだった佐藤輔子
東京の明治女学校で英語教師をしていた島崎藤村は、教え子である女学生・佐藤輔子に恋をします。
藤村のこの恋は、後に「初恋」という詩の中で詠われました。
まだあげ初めし前髪の
林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の
花ある君と思ひけり
やさしく白き手をのべて
林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実みに
人こひ初めしはじめなり
わがこゝろなきためいきの
その髪の毛にかゝるとき
たのしき恋の盃を
君が情に酌みしかな
林檎畑の樹の下に
おのづからなる細道は
誰が踏みそめしかたみぞと
問ひたまふこそこひしけれ
(島崎藤村「初恋」)
この「まだあげ初めし前髪の」女性のモデルが、佐藤昌介の妹であり、後に鹿討豊太郎の嫁となる佐藤輔子でした。
「初恋」のモデルには諸説あって、一人の女性に特定することは難しいようです。佐藤輔子はあくまでも、モデル候補の一人ということだったのでしょう。
しかし、藤村が輔子と知り合ったとき、輔子には既に親の決めた許嫁(鹿討豊太郎)があり、輔子への恋は、叶わぬ恋愛として終わりを告げます。
このあたりのことは、島崎藤村の自伝的小説『春』にも詳しく描かれました。
佐藤輔子の札幌での住所は北3条東3丁目の借家
札幌農学校の講師である鹿討豊太郎と結婚した輔子は、1895年(明治28年)6月、札幌で暮らし始めます。
新婚住居は「北3条東3丁目の借家」でした。
二人が結婚したのは明治二十八年の五月二十九日であった。新夫婦は札幌郡苗穂村一番地の五、栃内元吉の家に室を借りて住んだ。栃内元吉の妻すくは、輔子の義姉に当たっていた。(伊藤整「日本文壇史4」)
伊藤整『日本文壇史』では「札幌郡苗穂村一番地の五、栃内元吉の家に室を借りて住んだ」とありますが、豊太郎の長男・鹿討豊雄の『藤村の初恋の人佐藤輔』では「三姉(栃内スク)が自分の家近くにと言いながら用意してあった札幌北三条東三丁目の家に落ち着いた」とあるので、実際には「札幌北三条東三丁目の家」が正しかったようです。
ちなみに、現在の北3条東3丁目は、サッポロファクトリーの北向いの一画になりますが、サッポロファクトリーが、かつて札幌麦酒(現・サッポロビール)工場だったことからも分かるとおり、明治時代、この辺りは、様々な工場が建ち並ぶ産業地区でした。
 現在の北3条東3丁目界隈
現在の北3条東3丁目界隈現在、北3条東3丁目には、古い赤煉瓦の建物が遺されています。
「旧・福山商店」で、明治40年代の建築と言われていますから、もちろん、佐藤輔子の時代にはありませんでした。
輔子が住んだ地区から、すぐ隣にあるサッポロファクトリー(旧・サッポロビール工場)は大正時代の建築。
輔子が生きた時代にあった建物で、現在も残っているものと言えば、北海道庁の赤れんが庁舎(明治21年)と、札幌時計台(明治11年)くらいのものでしょうか。
輔子の時代、札幌開拓使麦酒醸造所(明治9年)は、当初、木造の建物だったそうです。
北3条の通りを、まっすぐ西へ向かうと、北海道庁赤れんが庁舎に突きあたります。
そのため、昔からこの通りは「開拓使通」とか「札幌通」などと呼ばれていました。
東6丁目には、北海道庁長官を務めた永山武四郎の旧邸も残るなど、札幌の歴史を知る上では、非常に大切な地区に、佐藤輔子は暮らしていたんですね。
ちなみに、熱心なキリスト教徒でもあった輔子は、札幌独立キリスト教会へ通いました。
札幌独立キリスト教会は、札幌農学校卒業生である内村鑑三や新渡戸稲造、宮部金吾、佐藤昌介らによって設立されたキリスト教会で、当時の住所は南3条西6丁目1番地(現在、札幌南三条病院がある一画)。
アカシアの白い花が咲く札幌で、輔子の新婚生活は始まっていたのです。
豊平墓地に埋葬された佐藤輔子の亡骸
1895年(明治28年)6月15日、札幌神社の例大祭の日に、輔子は24歳の誕生日を迎えますが、残された命は、実にはかないものでした。
1895年(明治28年)8月14日の『北海道毎日新聞』に、輔子の死亡広告が掲載されます。
鹿討豊太郎妻輔子儀豫テ病気ノ処養生不相叶今十三日午前六時半永眠仕候間此段辱知諸君エ御知申上候 但来ル十五日午後一時出棺南三条西六丁目会堂ニ於テ葬式執行 八月十三日 親戚 佐藤昌介 栃内元吉(『北海道毎日新聞』)
妊娠後、悪性の悪阻(つわり)に苦しむ輔子は、ほとんど食事を摂ることができずに衰弱して死んでいったと言われています。
伊藤整『日本文壇史』によると、「それは意志的に食事を拒絶しているような印象を周囲のものに与えた」そうです。
「輔子は藤村への思いを断ち切ることができず、自ら命を絶ったのだ」とする都市伝説は、このあたりの記述から生まれているのかもしれませんね。
自ら通った札幌独立キリスト教会で葬式が行われ、輔子の亡骸は遺品とともに豊平村にある共同墓地(豊平霊園)へと埋葬されますが、1984年(昭和59年)、豊平墓地の移転事業に伴い、輔子の遺品も東京へと移されてしまいました。
輔子の墓は豊平墓地のイ墓域のほぼ中央付近にあって、札幌市民見学会「さっぽろ散歩」=文学めぐり=の一拠点ともなっていた。移転工事は昭和五十九年九月八日に行われ、墓碑下を掘ったところ、輔子が愛用していた硯と硯箱のほか、金箔を打った櫛や香水の小瓶などが出土した。驚いたことには硯の中央が凹んでおり、輔子が勉学のために持ち歩いたことが推察された。遺骨は残念ながら九〇年もたっているため融解して、なかった。二四歳の若さで逝った輔子の遺品はいま東京都府中市の多磨霊園に納められ、永遠の眠りについている。(豊平墓地移転記念誌「聖地に星のまたたき」)
豊平墓地時代の輔子の墓には「鹿討輔子之墓」の文字が刻まれていたそうです。
まとめ
ということで、かつて文学散歩の聖地だった豊平墓地の移転により、島崎藤村の初恋の女性「佐藤輔子」を偲ぶものは、すっかりと失われてしまいました。
現在では、藤村の「初恋」のモデルの女性が、札幌で暮らしていた(札幌で死んだ)ことを知る人も少なくなってしまったのではないでしょうか。
せめて、鹿討豊太郎と輔子が新婚生活を過ごした地に、説明板くらいあってもいいんだけどなあ。
参考文献
及川和夫『藤村永遠の恋人 佐藤輔子』