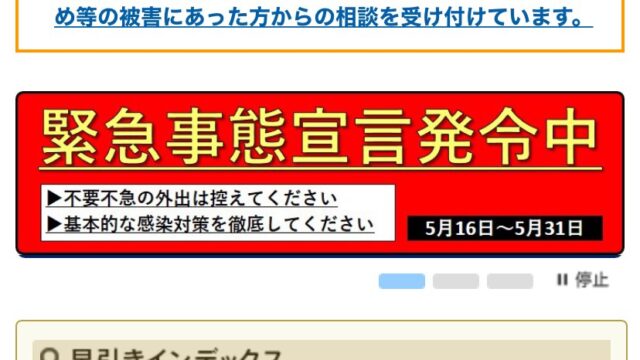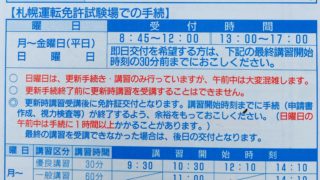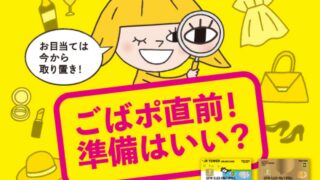1919年(大正8年)、16歳で単身上京した島木健作は、正則英語学校中等部最上クラスの夜学に通った。
この間、神田基督教会青年職業紹介部を通し、医者・弁護士等の玄関番をしながら、芝・神田・西大久保等を転々としていたらしい。
しかし、苦学の無理が祟ったのか、過労と栄養失調から病に倒れ、やむなく帰郷。
1920年(大正9年)、島木青年17歳の夏だった。
札幌では肺結核との診断を受け、多量の喀血から重体に陥ったこともある。
1921年(大正10年)、厚田村の網元から支援を受けることとなり、北海道唯一の私立中学校であった北海中学の四年編入試験を受けて合格。
「小説家・島木健作生誕地」の説明版では、西創成小学校から私立北海中学校へとつながっているように見えるが、実際には、苦難の上京を挟んでの北海中学進学だった。
北海中学では、雑誌部を文芸部と改め、『北中文藝』を創刊。
寄宿舎生活では、舎監の不正事件を暴いてストライキを先導するなど、正義感を揮ったという。
1923年(大正12年)、北海中学卒業後に再び上京、帝国電燈株式会社の株式係として勤めるが、9月1日、執務中に関東大震災に被災。
倒壊物の下敷きになるも、急死に一生を得て札幌に帰郷した。
札幌市南7条西1丁目1番地に下宿しながら、北海道帝国大学附属図書館に仕事を見つけ、1924年(大正13年)には、農学部農業経済学研究室へ異動。
このとき、研究室の教授は、かつて新渡戸稲造に師事したことのある高岡熊雄だった。
生活を切りつめながら貯金を続けていた島木青年は、1925年(大正14年)、三度札幌を離れて東北帝国大学法文学部専科に入学。
以後、札幌に戻ることはなかった。
政治活動が原因で東北帝大を追われた島木健作が、やがて共産党に入党してからの活動は、一般に知られているとおりである。
こうして振り返ってみると、島木健作にとっての札幌は、東京で活躍するための力を蓄えていた時期と考えることができる。
困窮や病気と闘いながら、政治や文学を夢見て上京した一人の若者。
「小説家・島木健作生誕地」の碑を見ていると、そんな島木青年の大正時代を、つい思い浮かべてしまうのだ。
(2024/04/28 19:02:01時点 Amazon調べ-詳細)