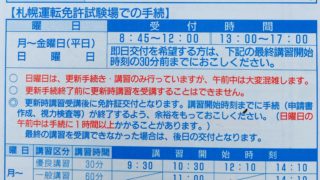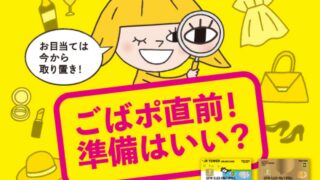作家・島木健作が生まれたの場所は、札幌区北一条西十丁目一番地である。
札幌北一条郵便局の前には、「小説家・島木健作生誕地」の説明板が設置されている。
もっとも、札幌市民でも、島木健作の名を知る人は、決して多くはないだろう。
まして、島木健作の作品を実際に読んだことがある人は、どのくらいいるのだろうか。
1903年(明治36年)9月7日、島木健作(本名:朝倉菊雄)は生まれた。
異父兄の八郎は、やがて、南4条西8丁目の島崎家へ養子に行くことになる。
宮城県気仙沼生まれの父は、北海道庁の官吏として働いていた。
現在の赤レンガ庁舎が現役だった時代で、札幌北一条郵便局からは、歩いて15分くらいだろうか。
日露戦争が始まると同時に父が病死。
1907年(明治40年)、母は子どもを連れて、南2条西9丁目の長屋へと移転する。
島木健作の困窮時代の始まりだった。
ちなみに、大火で函館を追われた石川啄木が来札するのは、この年の秋のことである。
わずか二週間の札幌滞在だったが、石川啄木(21)と島木健作(4)は、かなり近い距離で暮らしていたことになる。
さらに付け加えると、この時期、札幌には、詩人の野口雨情(25)も暮らしていた。
詩の都・札幌が、大正時代の日本詩壇に与えた影響は小さくなかったのだろう。
1910年(明治43年)、7歳になった島木健作は、南3条の公立西創成尋常高等小学校に入学、同学年には、やがて作家となる久保栄がいた。
西創成小学校は、後の札幌市立創成小学校で、札幌市内で最も古い小学校として知られている(2004年に資生館小学校へ再編された)。
1914年(大正3年)、11歳のときに、兄の在籍していた札幌師範学校附属小学校(現在の北海道教育大学附属小学校)に転入。
これは、月謝が必要なかったためだという(普通の公立学校では月謝の徴収があった)。
1916年(大正5年)に小学校尋常科を卒業して高等科に入学するが、母の体調が優れないことから、1917年(大正6年)に中途退学。
14歳にして、北海道拓殖銀行の給仕となって家計を助けた。
一方で、東本願寺別院の経営する夜学に通いながら勉学を続けているから、向上心の強い少年だったのだろう。
小説家になりたいと真剣に考えるようになったのも、この頃からだったらしい。
苦学の目的をもって上京するのは、1919年(大正8年)、島木健作16歳のときのことである。
現在、札幌市内で島木健作の痕跡を残すものといえば、札幌北一条郵便局前の「小説家・島木健作生誕地」くらいしかないらしい。
観光客には、こういう文化的なところを、もっと観ていってほしいものだと思う。
(2024/04/28 19:02:01時点 Amazon調べ-詳細)