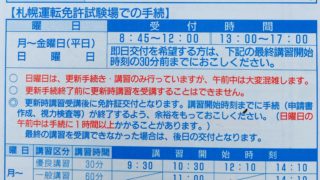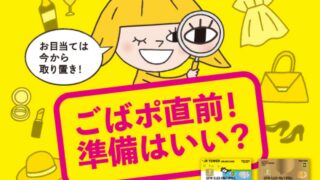「さっぽろライラックまつり」でも見ようかと思って大通公園まで出かけるが、相変わらずの雨。
強風注意報まで出ているので、とても歩く気になれない。
仕方ないので、久しぶりにさっぽろテレビ塔に入って、リラ冷えの街をぼんやりと眺めてみた。
渡辺淳一のセクハラ小説『リラ冷えの街』
「リラ冷え」というのは、北海道内だけで使われている季節の言葉で、5月に入って暖かった陽気が、ライラックの咲く頃に突然に寒くなることをいう。
桜の咲く季節に寒くなることを「花冷え」と呼ぶのと同じようなものなのだろう。
1970年代に流行した渡辺淳一の小説『リラ冷えの街』(1970)から定着したと言われている。
(2024/05/03 10:29:52時点 楽天市場調べ-詳細)
渡辺淳一は多くのセクハラ小説を残しているが、名作と伝えられる『リラ冷えの街』もかなりひどいハラスメント小説だ。
嫌がる人妻に無理やり酒を飲ませて酔ったところで強引にセックスし、妊娠しちゃったら中絶させてという、あからさまな男尊女卑の昭和小説なのだが、札幌の四季の移り変わりを背景に、美しい不倫物語として描かれている。
「まあ、話の筋はともかく」と、彼は思った。
『リラ冷えの街』というタイトルは、季節感があっていい。
特に、今日のように冷たい雨が降る五月の日曜日には。
「さっぽろライラックまつり」の歴史
大通の地下駐車場に車を入れて、オーロラタウンを歩いて、さっぽろテレビ塔に入る。
展望台は有料だが、三階の土産物売り場までは無料で上ることができる。
札幌市民には、さっぽろテレビ塔の展望台へ上ったことがないという人も少なくないだろう。
三階の土産物売り場は、観光客でいっぱいだった。
強い雨に遮られて、みんな行き場をなくしているのだ。
 大通公園ではリラの花が雨に打たれていた
大通公園ではリラの花が雨に打たれていた「さっぽろライラックまつり」を最初に考案したのは、札幌の文化人たちである。
当時の札幌は戦後の荒廃が著しく、見かねた文化人たちが「ライラックの咲く季節にビールでも飲みながら文化的なイベントをやろう」と言って始めたのが、1959年(昭和34年)から始まった「さっぽろライラックまつり」だった。
当時は「文化国家」という言葉が流行していて、市民の文化度の向上は、戦後社会の大きな課題だったのだ。
高度経済成長からバブル景気を経て、札幌市民の文化度が向上しすぎたのか、今ではライラックまつりが文化発展のためのイベントであったことさえ忘れられている。
「ワインガーデン」とか「ラーメンショー」とか、消費活動につながる「食文化」にだけは一生懸命で、芸術文化のことまで頭が回らないらしい。
中高生が参加する「ライラック吹奏楽」が、一番文化度の高いイベントだったのだが、今日の悪天候で今年は中止になってしまった(残念)。
さっぽろテレビ塔の三階から
さっぽろテレビ塔の三階から街を見下ろす。
注目の大通公園側が見えないのは「料金を払って見てください」ということなのだろう。
景観くらい無料で提供してやってもいいのにと、彼は思う。
 さっぽろテレビ塔の三階から創成川公園を見下ろす
さっぽろテレビ塔の三階から創成川公園を見下ろす西側の大通公園が見えないので、仕方なく、東側の創成川公園を見下ろす。
ここ数年で創成川の景観も大きく変わった。
河畔程度だったのが、本当に公園らしく整備された。
天気が良ければ下界へ降りて、創成川に沿って歩く価値はあるだろう。
 天気が良い日には創成川公園を歩きたい
天気が良い日には創成川公園を歩きたいいつまでいても仕方ないので、テレビ塔を出て、ジュンク堂書店で本を買って帰る。
地下駐車場に戻ると、既に満車で、多くの自動車が(場内で)順番待ちをしていて驚いた。
函館、帯広、旭川、北見、、、地方のナンバーが多い。
どうやら、ライラックまつりを観るためにやってきた旅行者たちらしい。
今日が雨でなければ、もっと良い休日になったのだろうけれど。
雨の中、自動車を出して、リラ冷えの街を通り抜ける。
大通公園でライラックの写真を撮るのは来週にしよう。