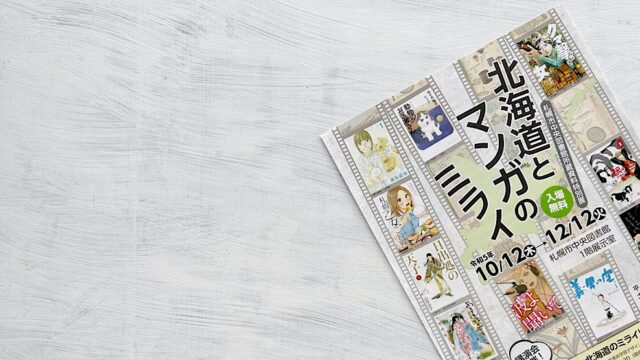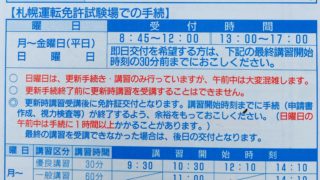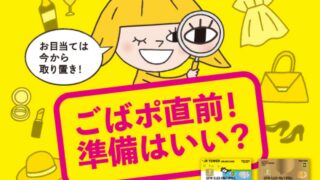旅をすると、自分の街が見えてくる。
住んでいるだけでは見えなかった良いところや良くないところ。
旅に出て、札幌を知ろう。
そんな「さっぽろ旅くらべ」、今回はニューヨーク・タイムズが選ぶ「今年行くべき世界の旅行先」で世界第2位にランクインした街・盛岡へ、小さな旅に行ってきました。
なぜ、盛岡市が、世界第二位になったのか、その理由が分かったような気がします。
コンパクトなサイズ感は散策にぴったり
 文学館「もりおか啄木・賢治青春館」は、盛岡文学散歩の拠点だ
文学館「もりおか啄木・賢治青春館」は、盛岡文学散歩の拠点だ盛岡の旅は、文学の旅だ。
街の至るところに、石川啄木と宮沢賢治の文学碑がある。
地図を片手に文学碑巡りをするだけで、盛岡の街に詳しくなってしまうかもしれない。
意外と、徒歩だけで回れてしまうくらい、盛岡の街はコンパクトだ。
このコンパクトな感じは、札幌にはない。
散策をするのに、ちょうどいいサイズ感。
文学館「もりおか啄木・賢治青春館」を中心に、石川啄木と宮沢賢治ゆかりの地を訪ねて歩いてみた。
いーはとーぶアベニュー材木町は宮沢賢治の世界
 「いーはとーぶアベニュー材木町」は、宮沢賢治の世界そのもの
「いーはとーぶアベニュー材木町」は、宮沢賢治の世界そのもの盛岡のヒーローは、やはり宮沢賢治だ。
「いーはとーぶアベニュー材木町」は、まるで宮沢賢治の世界そのもの。
あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。(宮沢賢治「ポラーノの広場」)
「モリーオ市」のモデルは、もちろん盛岡市。
旅行から戻ったら、真っ先に『ポラーノの広場』を読んでみようと思った。
盛岡市民に愛されている宮沢賢治
 街の書店でも宮沢賢治は特別の存在だった
街の書店でも宮沢賢治は特別の存在だった盛岡の人は、宮沢賢治に親近感を持っているらしい。
花巻駅から空港まで乗ったタクシーの運転手さんは、訊いてもいないのに、宮沢賢治の話をしてくれる。
「そこに賢治先生の家があるんですよ」
そう言えば、街の本屋を覗くと、宮沢賢治のコーナーがちゃんとあった。
中途半端なゆるキャラなんていらないくらい、宮沢賢治は盛岡のキャラクターだ。
石川啄木の青春時代を辿る
 盛岡駅前の啄木歌碑の裏側にある古い解説版「啄木であい道」
盛岡駅前の啄木歌碑の裏側にある古い解説版「啄木であい道」文学碑の数は、宮沢賢治よりも、石川啄木の方が多いかもしれない。
と思われるくらい、街のあちこちに啄木の歌碑がある。
たった二週間しか滞在しなかった札幌と違って、盛岡は、啄木にとって青春の街だ。
青春の歌が、盛岡の街には溢れている。
定番施設「啄木新婚の家」もいいけれど、「石川啄木・若山牧水 友情の歌碑」のように、ちょっと変わった文学碑もいい。
啄木が東京で病死したとき、詩人仲間で臨終に立ち合ったのは若山牧水だけだった。
「友情の歌碑」というのも温かくて、何だか盛岡らしいような気がする。
盛岡駅前の啄木歌碑の裏側に「啄木であい道」という、古い説明版があった。
古いモノを撤去しない姿勢に好感が持てる。
札幌ともゆかりの深い新渡戸稲造の出身地
 盛岡出身の新渡戸稲造は札幌農学校の卒業生だった
盛岡出身の新渡戸稲造は札幌農学校の卒業生だった盛岡は、新渡戸稲造の出身地でもある。
札幌農学校出身の新渡戸稲造は、もちろん札幌との縁が深い人物だが、盛岡の人の新渡戸稲造に対する敬意はすごい。
なにしろ、あちこちに新渡戸稲造の像や碑がある。
つまり、盛岡という街は、歴史を大切にする街なんだろうな。
生家跡を公園にした「新渡戸稲造生誕の地」は、地元出身の偉人に対する誇りが感じられる。
札幌の「遠夜夜学校跡地」なんか、恥ずかしい感じがするくらい(笑)
北星女子高校の名付け親が、新渡戸稲造であることを知っている札幌市民は、どのくらいいるだろうか。
文学マップは盛岡の散策ツール
 街の随所にある文学マップは散策ツール
街の随所にある文学マップは散策ツール街の随所にある文学マップも、盛岡の散策ツールになっている。
観光スポットが点ではなく、しっかりとした線で繋がれているのだ。
市民の共通理解があるからこそ、貴重なリソースをトータルコーディネートできるのだろう。
簡単そうなことだけれど、役所が旗を振るだけでは、こういう取組は難しいかもしれない。
盛岡はレトロ建築の宝庫
 黄色いスクラッチタイルの「岩手県公会堂」
黄色いスクラッチタイルの「岩手県公会堂」ニューヨーク・タイムズでも、盛岡の魅力の一つとして紹介されているが、街を歩くと、歴史的建造物が目に付く。
観光スポットというよりは、日常生活の中に溶け込んでいる感じの建物たち。
観光ガイドで探し当てていくよりも、偶然に見つけた建物の方がうれしい。
例えば、黄色いスクラッチタイルで、すぐに昭和初期の建築と分かる「岩手県公会堂」。
北海道大学の農学部を小さくしたような建物は、佐藤功一の設計によるものだ。
こういう建物が、現在も現役で活用されているところがいい。
北上川、中津川、雫石川の流れに沿って散策
 川が流れる自然が満ちている盛岡市内
川が流れる自然が満ちている盛岡市内盛岡を散策していると、やたらに橋を渡る。
ニューヨーク・タイムズで「川が流れる自然が満ちており」と書かれているとおりだ。
北上川、中津川、雫石川の流れに沿って散策するのも楽しいし、橋を越えながら盛岡の街を散策するのも楽しい。
川から吹いてくる風って、どうしてこんなに気持ちいいんだろう。
朝の出勤時間帯でも、盛岡の街は混雑していない
 朝の出勤時間帯でも、盛岡の街は落ち着いた雰囲気だった
朝の出勤時間帯でも、盛岡の街は落ち着いた雰囲気だったニューヨーク・タイムズには「人混みを避けて歩いて回れる珠玉の街」と紹介されているけれど、朝の出勤時間帯でも、盛岡の街は混雑していなかったような気がする。
通勤の人たちがいないわけではなく、ちょうどいい距離感を保って人が歩いている感じ。
札幌みたいに外国人観光客が多すぎるということもない(ホテルには外国人も宿泊していたけれど)。
盛岡みたいなサイズの街にインバウンドが集中したら、あっという間にオーバーツーリズムになってしまいそうな気がする。
いわて花巻空港に流れる「緑の町に舞い降りて」
 いわて花巻空港に、ユーミンの「緑の町に舞い降りて」が流れていた
いわて花巻空港に、ユーミンの「緑の町に舞い降りて」が流れていたいわて花巻空港には、ユーミンの曲が流れていた。
1979年のアルバム『悲しいほどお天気』収録曲の「緑の町に舞い降りて」。
さざ波はるかに渡ってゆく
飛行機の影と雲の影
山すそかけおりる
着陸ま近のイヤホーンが
お天気知らせるささやき
MORIOKAというその響きが
ロシア語みたいだった
松任谷由実「緑の町に舞い降りて」
この曲は、iPhoneのプレイリストにも入れているお気に入りの一曲。
派手なキャンペーンソングじゃないから、盛岡の街にちょうどいい感じ。
ユーミンも、きっと、盛岡の街が好きになったんだろうなあ。
盛岡冷麺と焼き肉をリピート
 二泊三日の旅行で、盛岡冷麺と焼き肉をリピート
二泊三日の旅行で、盛岡冷麺と焼き肉をリピート「盛岡三大麺」と呼ばれているのは、盛岡わんこそば、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺の三つ。
全部食べたけれど、このうちリピートしたのは盛岡冷麺だけだった。
最初の夜は「ぴょんぴょん舎」、最後のランチは「大同苑」。
どちらも焼き肉と一緒に食べたけれど、焼き肉と麺が、こんなにマッチするなんて、なんだか不思議だ。
「大同苑」の盛岡総本店では、前沢牛と冷麺がセットになった「上焼肉ランチ」をチョイス。
冷麺と焼き肉食べるためにも、いつかまた盛岡へ行きたい。
お土産は地元のクラフトビール「ベアレンビール」
 盛岡旅行で買ったお土産たち
盛岡旅行で買ったお土産たち盛岡旅行のお土産。
地元のクラフトビール「ベアレンビール」と千代の亀酒造「日本酒 銀河鉄道」は、お酒の好きな妻へのお土産。
宮沢賢治が好きな娘へのお土産「賢治手拭い(星めぐりの歌)」と「賢治キーホルダー(雨ニモマケズ)」と「宮沢賢治の豆本(『銀河鉄道の夜(上下)』」は、「もりおか賢治・啄木青春館」で購入したもの。
文学館「もりおか賢治・啄木青春館」のミュージアムショップは、商品のラインナップがかなり充実していた。
札幌の「北海道立文学館」の方が立派な施設なのに、お土産は断然に盛岡の方が充実している。
なぜだ?
まとめ
 盛岡は文化度の高い大人の街だ
盛岡は文化度の高い大人の街だ盛岡と札幌を比べてみて思ったこと。
盛岡の街は、文化度の高い街だ。
上品な大人の街と言ってもいいのかもしれない。
下品で押しつけがましい観光業じゃなくて、市民が誇りを持って街を作っているという感じ。
特に、ゆかりの人々に対する敬意がすごい。
文化人への敬意が、そのまま盛岡の観光を支えるエネルギーとなっている。
うちの街は、こんなに凄いんですよという誇り。
対して札幌は、今や旅行者のための街だ。
観光客が喜ぶイベントと、観光客が喜ぶお土産品。
まあ、それはそれで悪くないのかもしれないけれどね。