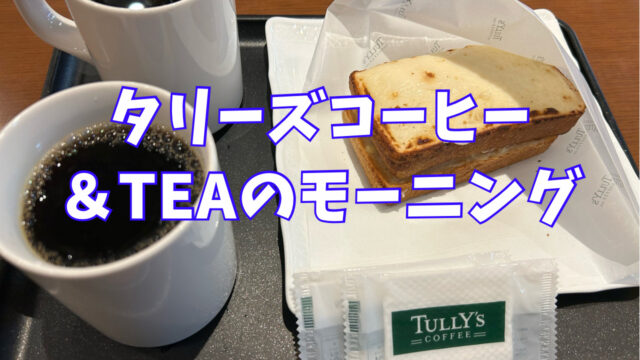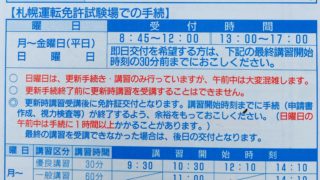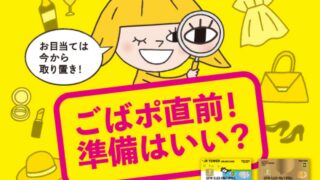道内の小学校で、熱中症による死亡事故があったらしい。
【伊達】22日正午ごろ、伊達市元町の伊達小(花田啓光校長、児童数496人)の校舎内で小学2年の女子児童(8)が倒れたと、同校から119番があった。救急隊員が駆けつけたところ、女児は意識不明の重体で、病院に搬送されたが間もなく死亡した。西胆振行政事務組合消防本部によると、女児は熱中症の可能性があったという。(『北海道新聞』2023/08/23朝刊)
昨日の伊達市内の最高気温は、統計開始以来最高の33.5度だったという。
現在、北海道では、連続真夏日記録を更新中(昨日で34日連続)。
「北海道の夏は涼しい」という古い常識が通用しなくなっている。
現代の北海道は、もはや避暑地でさえないのだ。
過去の記録を拾ってみる。
一昨年2021年の札幌で、8月に30度を超えたのは10回で、最高気温は35度。
50年前の1973年(昭和48年)では、同じく8回で、最高気温は32.7度。
昔の北海道でも真夏日はあったけれど、最高気温は高くなっているような気がする。
ちなみに、終戦の年の1945年(昭和20年)8月では、30度超えが8回、最高気温が33度だった。
8月15日の終戦記念日は最高気温が23.9度と涼しかったが、17日以降は30度を超える猛暑となっている。
敗戦と猛暑と空腹を乗り越えて、当時の人たちは生き延びなければならなかった。
飽食の現代、敵は、飢えでもアメリカでもなく、熱中症である。
熱中症は、環境・体調・行動の三要素の組み合わせで引き起こされる。
気温が高い、湿度が高い、風がないなど、環境にリスクがあるときには、体調管理と行動管理で、熱中症リスクを軽減するしかない。
札幌市教育委員会によりますと、市立の小学校198校の内44校を23日、暑さのため臨時休校とし、市立の幼稚園9園の内1園も、同じく暑さのため臨時休園としました。(北海道放送(株)2023/08/23)
熱中症対策に関するリスク・マネジメントは、今後一層多様化していくだろう。
もっとも、我々が子どもの頃には「熱中症」という言葉などもなかった。
炎天下にやられる病気といえば「日射病」で、帽子さえ被っていれば、日射病は防げると考えている親も多かったように思う。
「鬼の霍乱(かくらん)」の「霍乱」も、日射病のことだと教わったのではないだろうか。
「熱中症」の用語が一般に定着するのは、2000年(平成12年)頃から。
昔は、炭鉱労働者に多い病気だったが、現代の学校は、かつての炭鉱と同じくらいに生活環境が悪化しているらしい。
つくづく古い経験が信用できない時代だと思う。
大切なことは、子どもたちの事故を防ぐことだろう。
そのためにも、我々大人たちの常識を変えていかなければならない。
古い経験でリスク管理をする時代は、とっくの昔に終わっているのだから。